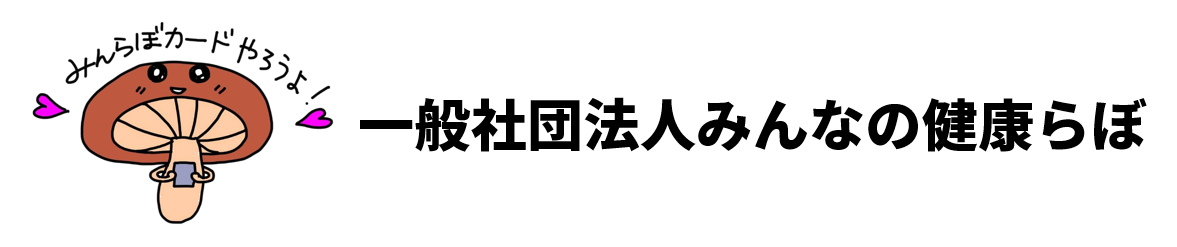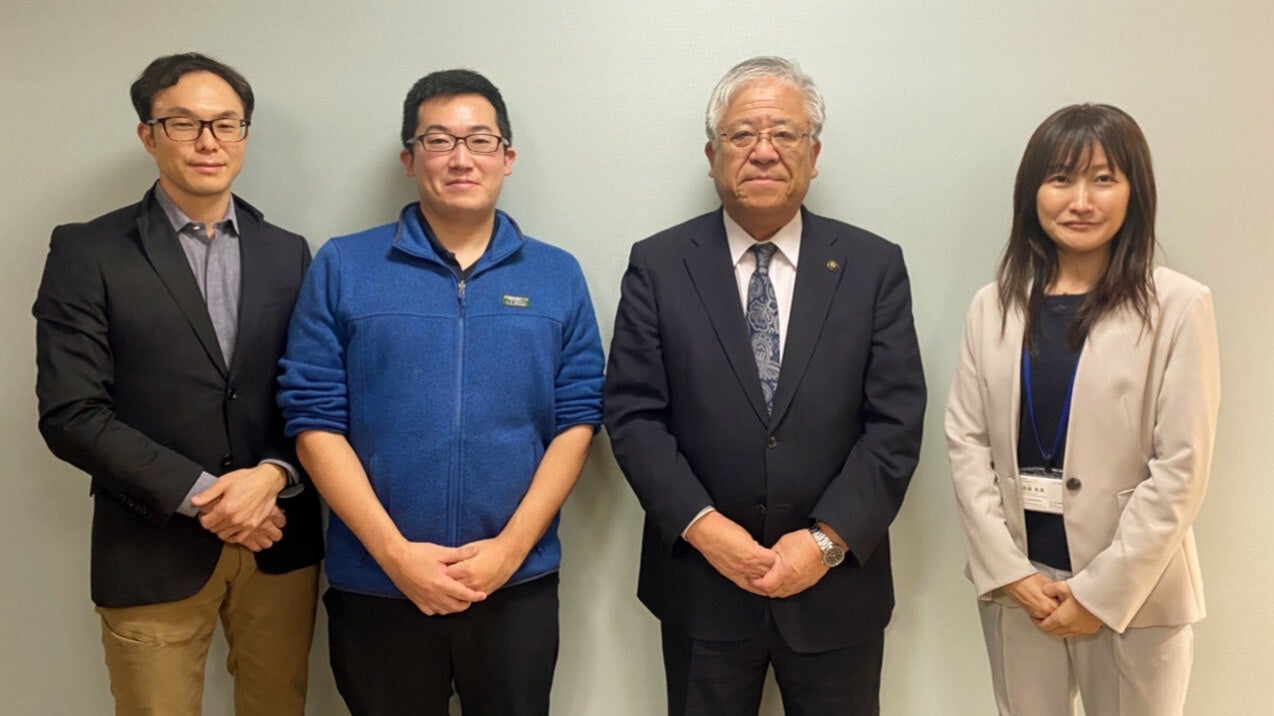12月16日、登米市の熊谷盛廣市長に、登米市の急病者に対する救急搬送件数が、やまと在宅診療所登米の開設前後で減少したという研究成果を報告しました。これは、2024年8月、 The Tohoku Journal of Experimental Medicine に掲載されたものです(原著は以下よりダウンロードください)。
結果の概要は以下の通りです。
- 目的:訪問診療の普及によって地域の救急搬送件数は減少するのかどうかを疑似実験的に検討した。
- 方法:宮城県登米市における、65歳以上の急病者に対する救急搬送件数を、同市の年齢分布に従って標準化した。
- 結果:2013年のやまと在宅診療所登米の開院前後で救急搬送件数の増加度は減少した。具体的に、標準化救急搬送件数は、2005年の61.8%から2010年の73.2%へと年々上昇する中で、東日本大震災が生じた2011年に急上昇し、2012年には89.6%と高水準を維持した。その後、同件数は、同院が開設された2013年から2017年まで徐々に低下した。
- 結論:在宅療養支援診療所は、在宅療養患者に医療サービスを効果的に提供したことにより、救急搬送の減少に寄与した可能性が示唆された。
研究成果はPRTIMESでプレスリリースしました。
毎日新聞でこのプレスリリースが取り上げられました。
熊谷市長はデータ結果を迅速に読み取り、「この結果は明らかです。やまと在宅診療所登米の地域貢献は、市民の反応を見れば分かります」と述べられました。
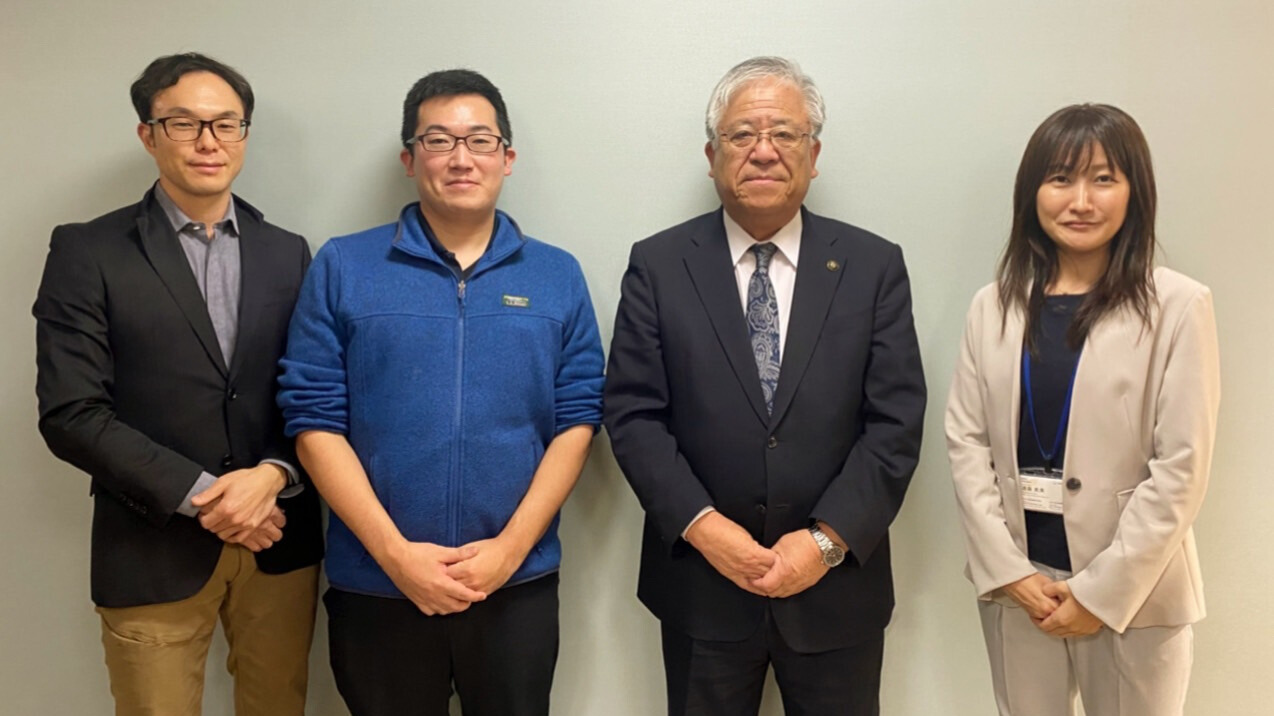
本研究は、やまと在宅診療所登米と山形大学の共同研究体制に加え、みんらぼの協働によって実現したものです(詳細は以下を参照ください)。このような市長からのコメントを受けて、本研究の意義がさらに深まったと感じています。
在宅療養支援診療所の利点と救急搬送件数への影響
在宅療養支援診療所の特徴は、通院が困難な患者の住まいを訪問する体制にあります。この仕組みは、患者の体調変化にいち早く気づき、迅速に対応することが可能であり、結果として地域全体の救急搬送件数を抑制している可能性があります。
また、診療所に通院している患者が、予期せぬ状態で自宅等で呼吸停止した場合、特に夜間やかかりつけ医が対応できない際には、救急搬送が必要になることがあります。しかし、在宅療養支援診療所では、こうした状況でも救急搬送を介さず、自ら訪問して死後診察を行う体制が整っています。これが今回の結果に寄与していると考えられます。
POLSTの導入とその意義
一方で、在宅療養支援診療所にかかりつけではない患者でも、自宅で延命治療を受けずに最期を迎えたいという願いを持つことがあります。このような患者の意向を尊重する取り組みとして、各自治体で進められているのが、生命維持治療に関する医師の指示書(Physician Orders for Life-Sustaining Treatment [POLST])です。
POLSTは、患者が医師と相談し、生命維持治療の実施や中止に関する指示を明記した文書です。この文書に「心肺蘇生を行わない」との指示がある場合、家族が呼吸停止した患者を見て119番通報しても、救急隊は指示に従い心肺蘇生を行わない流れとなります。
みんらぼの杉山理事は、一関消防本部がPOLST(2024年10月施行)を策定する際の意見交換に参加した経験を持っています(詳細は以下を参照ください)。
今後の期待
市長への報告後、データ提供にご協力いただいた登米消防本部にも研究成果をご報告しました。登米市においても、POLSTの取り組みが広がり、患者の意思を尊重した地域医療がさらに進展することを期待しています。